「蜜柑」の読書感想文
汽車の外、3人の子供が叫ぶ暮色の空に、窓から飛び出した蜜柑の色が輝く。それはまるで太陽のようであった。霜焼けした手に三等切符を握り締めた少女はしっかりと風呂敷を抱えて座っていた。
これは芥川龍之介の短編、蜜柑のワンシーンである。実際にはもっと古語が並び、情緒があるシーンなのだが、これを読んだ時私は驚愕した。
こんなにも色が見える文章があるのだろうかと。主人公の男が冒頭でコートの中に手を突っ込むシーンがあり、少女の手も霜焼けとあるようにおそらく季節は冬なのだろう。
そんな冬に蜜柑を持って汽車の外へ投げる少女。それだけを聞くと到底不可解なことに思えるが、そこにはちゃんと理由がある。
主人公の男は始め、二等客車にやってきたこの霜焼けの少女のことを快くは思っていなかった。都会に奉公に出るのであろう、髪は油っ気もなくボサボサで頬は割れ、頬は寒さで真っ赤だ。服装も不潔でいかにも田舎者といったいでたちである。
ついにはここは二等客車であるというのに三等客車の切符を握りしめているではないか。不快な少女の存在を忘れようと新聞に目を落としたが、いつの間にか少女は自分の隣の窓を開けようとしていた。何故こんなところで。
程なくして窓が開くと一気に煙が中に紛れ込み、喉があまり強くない男はむせ返る。こんな気まぐれで何を考えているんだと憤慨する彼を全く気にもせず、少女は汽車の行く先を見つめている。
と、トンネルから汽車が抜けると、貧しい町外れの踏切にさしかかる。少女は窓から半身を乗り出した。まさに踏切を通り過ぎんというところで3人の背の低くて顔の赤い子供たちが一斉に歓声をあげる。
そして少女は、懐から取り出した蜜柑を投げた──ここまでが蜜柑が太陽に変わるまでの経緯である。寒空の下、色のない貧しい街並み、汽車の煙、そんな灰色の世界の中で蜜柑だけが明るく輝く。
男はこの刹那、先ほどの子供達は奉公へ行く少女を見送りに来ていたのだと理解する。そして、蜜柑は弟達の労に報いるためのものだったのだと。これが少女の不可解な行動の理由だ。
怒りが最高潮まで達していた男であったが、目に焼き付いて離れないその蜜柑の輝きは、男の胸に深く刻まれ、退屈で灰色な彼の日常に、一筋の日の光が差したのである。このように男の心の対比もしっかりと蜜柑とその他の灰色のように付けられている。
短編であるのにもかかわらず、このインパクト。他にも色がついた作品はあるだろうか。芥川龍之介の作品を読もうとおもうきっかけとなった。
(20代女性)
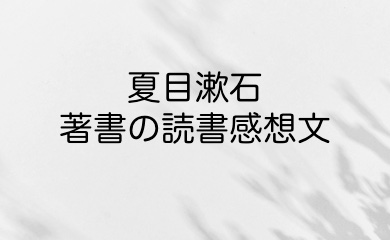
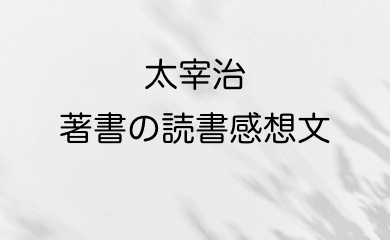
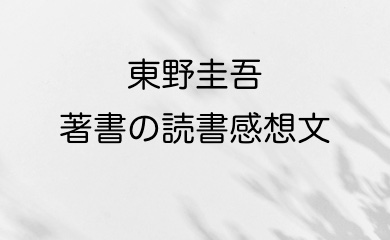
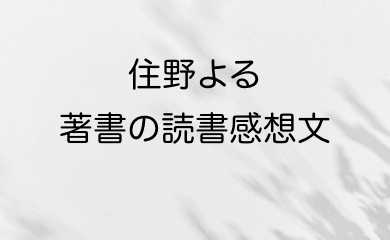






















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!