「地獄変・偸盗」の読書感想文
私はこの本を読み終わった時に、芸術至上主義を極めた芸術家の悲しみが、私の心に突き刺さった。愛する娘が死ぬことさえも、自分の芸術の集大成を描くために、その事実を受け入れた。
また、自分が今までにない地獄の様子を味わうためには、愛する娘を犠牲にすることを心のどこかで望んでいた。
これまでにない業火の中、悶え苦しみながら死んでいく愛する娘の様子を「さながら恍惚とした法悦の輝きを、皺だらけな満面に浮かべながら」描いた良英の描き終わった後の虚無感とは、どんなに深い恐ろしいもの、辛いものであろう。
愛する娘を失った悲しみや孤独、芸術への未練がなくなり、心にぽっかりと穴が開いたような、もう生きる意味のなくなった良英の虚無感を考えると、ぞっとする。
良英の芸術至上主義の姿勢をへし折ろうとしていた大殿に「出かし居った」と認められた後、縊れ死んだ良英は、あの世で娘と何からも邪魔するものなく、純粋に娘のことだけを考えて過ごしているだろうか。
車に「罪人の女房が一人、縛めた儘、乗せ」た女房が自分の娘だと分かった瞬間、「良英の心に交々往来する恐れと悲しみと驚き」に襲われた姿は、間違いなく、愛する娘を想う父親の姿であった。
それが、日頃、娘が可愛がっていた猿も一緒に業火へ入った瞬間、「さつきまで地獄の責苦に悩んでゐたやうな良英」が父親としての想いから解き放たれ、芸術家としての良英へと切り替わる。
良英という愛称の猿を自分の姿に重ね合わせ、自分も娘とともに地獄へ落ちることを覚悟したのだ。自分の分身としてみんなに扱われていた猿がともに死んでいく様子は、娘が焼かれ死んでいく現実を受け入れるための救いになったのかもしれない。
芸術家として生きた良英は、真の芸術家であった。良英の芸術を邪魔しようと企て、良英の娘を焼き殺す大殿は、「唇を御噛みになりながら、時々気味悪くお笑ひになつて」いるような人の気持ちを持たない冷酷で野蛮な人間である。
この二人の様子で充分、良英と大殿の勝敗は決している。娘の死を受け入れ、大殿を超越した良英は、娘を想う優しい父親であり、偉大なる芸術家である。どれをとっても、大殿は良英を超えることはできないであろう。
何にもとらわれない、芸術のことだけを純粋に考える芸術至上主義とは、全てを超越した素晴らしい姿勢である。ただ、その代償は大きく、娘を失い、芸術への未練もなくなった良英のことを想うと、辛く深い悲しみしか残らない。
良英は芸術家として生きたことに悔いはないのだろうか。それほど、芸術とは、とりつかれると恐ろしいものなのだろうか。
(30代女性)
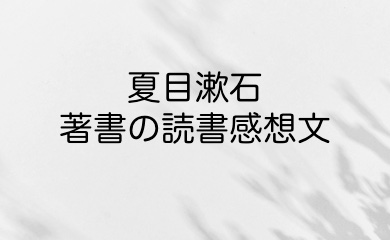
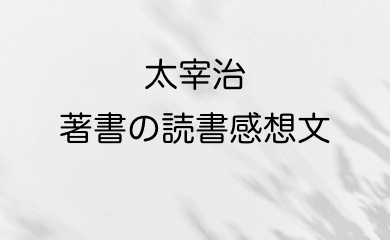
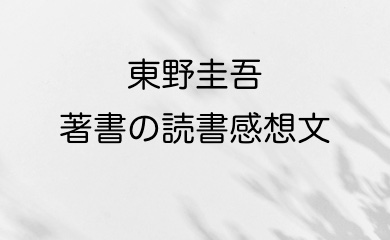
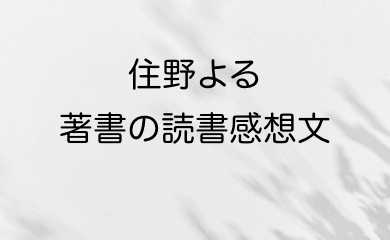





















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!