「蜘蛛の糸」の読書感想文①
この作品は子供のころから何度か読んだが中学生の夏休みに課題図書で読んだ思い出が一番はっきりと覚えている。お釈迦様が悪いことばかりしてきていた主人公犍陀多に生前蜘蛛を助けたという理由で一度だけチャンスをあげたことがすごく印象的だったのを今でも覚えている。
この作品は子供の時に何度も朗読で話を聞いていたが、そのたびにとても怖い作品だと思い、私は犍陀多が罪人だから地獄に行ってしまったというよりもお釈迦様はとても怖い存在でこのお釈迦様を生前に怒らせた人間たちこそが地獄に行くべき人々なんだと解釈をしていた。
だから罰を受けるために恐ろしい地獄へ連れていかれるのだと思いこんでいた。作品の中では細かく犍陀多の背景は描かれていない。
あくまで盗みを働いていたことだけが描かれている。ただ、子供ながらきっと盗みなどをしなければいけない理由や環境だった男なんだろうと思い本を読んでいた。
それは、根っからの悪い人間が小さな命を急に助けるようなことがあるとは考えられなかったし、目にも留めないような小さな命を気にする人間が悪い人間とも思えなかったからである。
ところで自分の人生において本を読んだ後も色々と考えさせられた最初の本がこの「蜘蛛の糸」だった。そう考えると芥川龍之介の想像力、そして独創性と言葉の説得力はすごいと思う。小学生でも理解が出来かつ大人も楽しめる文章を書ける芥川は素晴らしい。
この一言に尽きる。ここまで才能のある人間が若いうちに死んでしまったと思うと日本は大きな財産を早々になくしてしまったのだと残念さも感じる。
しかし、私はこの作品を久しぶりに読んで感じたことは芥川は犍陀多としてこの本を書いていたのだろうか?誰でも間違いはあり、誰でも人を傷つけたことは一度や二度はあるだろう。彼はなにを感じて書いていたのだろうか?
そして、この作品を読み思うのは「もし自分が犍陀多だったらどう行動しただろうか?」どうしてもこのことは深く考えてしまう。
実際に子供たちに教えるとすれば「自分よりも弱い人や他人には優しくしないとだめだよ。蜘蛛の糸は細いから周りの人に蜘蛛の糸をゆずって順番に上るんだよ」こんな回答を本音で言えるのだろうか?本の中では犍陀多は地獄の地の底にいる。
そこはどこを見ても真っ暗で針の山がたまに見えるような場所だということだ。もし自分がこの世界にいたら人に優しくできるような正常な気持ちではいられないだろう。でも、お釈迦様はどうしたかったのだろうか?
確かに犍陀多は蜘蛛を助ける姿を見せたことによってお釈迦様から認められて蜘蛛の糸をもらうチャンスをもらった。しかし、どうしても私にはお釈迦様が犍陀多を試したかったようにしか考えられない。
でも、実際に自分は交通事故にあった経験があるのだが一番のけが人だった私は傷だらけだったにも関わらず他の人を助けていたという経験がある。
これは理由とか感情とかそんなものではなかった。ただ動いていたのだ。そう考えると私が犍陀多だったら上りたい気持ちはあるものの結局そのことを言わずに他人が上っていくのをいつまでも地の沼で見ていたかもしれない。
そして、お釈迦様は犍陀多を見極めるためのチャンスを自身のために糸を降ろしたのかもしれない。とにもかくにも人の死後を決断するお釈迦様が一番苦しい立場であろう。
タイムリミットはなくいつまでも天国にいつづける。そんな彼の生活も逆に孤独で犍陀多のいた地獄のような生活なのではないかと考えてしまう。
(30代女性)
「蜘蛛の糸」の読書感想文②
「蜘蛛の糸」は有名すぎるので誰もが知っている小説ではあるが、あらためて読んでみると数ページ足らずの文章のなかに考えぬかれた内容で構成され、その文面からは漂ってくる匂いまで感じられる。そもそも「蜘蛛の糸」という題名がすごい。
虫や昆虫が好きな私には「蜘蛛の糸」と聞いただけで何が書いてあるのか知りたくなってしまう。お話は、時間の流れも忘れてしまうほど和やかな雰囲気の極楽と、色々な責め苦に疲れ果てて泣き声すら出せなくなった地獄の罪人の様子から始まる。
お釈迦様は暇そうに朝の散歩をしている。極楽からは、その池の水を通して地獄の様子が見えるらしい。この蓮池を覗き込んだお釈迦様は地獄の血の池で苦しんでいる一人の男に気付く。
その男は人を殺したり家に火をつけたり、その他いろいろな悪事をした罪人である。但し、こんな男でも道端を這っている小さな蜘蛛の命の大切さに気づき、踏みつぶさないでそのまま行かせたことがあるらしい。
お釈迦様はそれを善い行いと考え、地獄から這い上がるための糸「蜘蛛の糸」をその男の真上に垂らしてあげた。
普通に考えれば蜘蛛の糸では登れる訳がないと思うが、蜘蛛の糸は1ミリの太さがあれば人一人、鉛筆の太さならばジェット機が吊るせる程強靭で、人工的に製造する研究が世界的に行われているそうだ。
それはともかく、その男は蜘蛛の糸を這い上がり、途中で休憩する。下を見ると他の罪人が蟻の行列のように蜘蛛の糸を這い上がってきている。
これを見た男はこれでは糸が切れてしまうと思い、俺の糸に勝手に上るなと喚く。その途端、蜘蛛の糸は男がぶら下がっている処からぷつりと音を立て切れてしまう。当然、男はさっきまでもがき苦しんでいた血の池に落ちてしまった。
これを一部始終見ていたお釈迦様は何事もなかったかのように蓮の花の匂いがたちこめる極楽をふらふらと散歩し始める。お釈迦様は、せっかく男の善いところに温情をかけたのに、他人を押しのけて自分だけ助かろうとしたその男の無慈悲な心に減滅したのだと思う。
そもそも人殺しなどの悪行をした男を最初から許す気などなかったのだ。人間とはかくもあさましい生き物だということを、お釈迦様の戯れ心を通して感じることができる。
私には独善的なところがあり、直ぐに自分の意思は相手に伝わっているという思い込みをしてしまうことがある。でも自分の伝えたい気持ちを周りの人に理解してもらうには、相当の努力や工夫が必要だということを本小説から学んだと思う。
相手に上手く伝える努力しなければならないということを心に留め置いて、人生をより豊かなものにしていきたいと感じたのである。
(60代男性)
「蜘蛛の糸」の読書感想文③
誰しもが一度は読んだことのある名作中の名作「蜘蛛の糸」を読み感じた事は、自分の中にも他人の中にも人を蹴落として自分だけが助かりたいという感情や欲があるということだ。
私たちは普段は一枚皮を被り、欲は汚いと扱う。強盗となって人様のものを盗むなんてと批判し、さも自分はそんな事をしないと思っている。
そして、もし自身がその状況に追い込まれたら?というのを考えてすらいないだろう。いざ追い込まれたら、例えば家も財産も無くなり路頭に迷い乞食同然になれば私は迷わず盗みにも走るだろう。
もし地獄に落ちた時、極楽へ繋がる一本の細い糸が垂れ下がっていたら他人を押しのけてでも縋り、他人を蹴落とすかもしれない。
芥川龍之介はここの部分をありありと見せつけた。人のもっと深い欲望の部分を文章で巧みに表現したと思う。私がこの本から得たものは、自分の中にもこんなものが巣食っているという事実を見せつけられそれを知る事が出来たことだ。
もちろん普段はそんな事はしないと思いたい。しかし、いざこの様な状況になった時にこの主人公と同じ行動をしてしまうのではないか、という恐ろしさも感じた。本当に怖いと思った。そして、それが他人にも同じ様にあるというのにも恐怖を感じる。
しかし、その感情を自分が持っているということを知れたことが良かったと感じている。自分の中にもあると分かるから、ある意味で冷静にもなれる。この他人を蹴落としてでもという感情が湧いた時に、本を思い出しハッとさせられ現実に引き戻してくれるかもしれない。
そして、一歩引いた立場から状況を知る事ができ冷静に行動する事ができるかもしれないと思った。考え過ぎなのかもしれないが、でもこの本から得たこの感情は大切にしたいと感じた。
本は大切な事を教えてくれるものである。綺麗な事も時には汚い事も様々な主人公の生き方を通して学べるのであると思っている。だから、この蜘蛛の糸の主人公から学び得た事もきっといつか必要になると思っている。以上が、私がこの本から得た事だ。
(20代女性)
「蜘蛛の糸」の読書感想文④
この作品を読んで感じたことは、人間であればほとんどの人がこの作品に出てくる地獄の罪人カンダタのような状態にもしなったら、きっとみんなカンダタと同じことを言うと思う。
中には心がとても広くてそう言わない人もいるかもしれないが、私だったら、カンダタと同じように「自分の所に来た糸なんだし、こんなに人がぶら下がったら糸が切れちゃうからみんな降りろ。」と言うはずだ。
きっとみんなそう言うと思う。だからこの作品では私は地獄へ落ちる。きっとみんなも地獄へ落ちる。極楽へ行ける人はほんの一握りだと思う。だから極楽なのだろうか。
この作品では極楽から地獄を見下ろす感じで見ることが出来るが、地獄からは真っ暗で極楽を見上げることが出来ない。極楽は光があって明るいが地獄は光がなく暗い。この事は景色や周辺の明るさだけでなく、心の中の明るさも表していると思う。
その理由は地獄では針の山や血の海でかなり暗い気持ちになるのに対して、極楽では、「極楽」と言う所に居ると思うだけで気分が良くなる気持ちになるだろう。
「極楽」と「地獄」の差は何と言っても罪を犯したか、そうでないかだ。だから前文で地獄行きと言ったが、我々は罪を犯してはいない。だから極楽へ行けるだろう。さらに極楽と地獄では物の見方が全く違うと見える。
この作品の中では、蜘蛛の糸でも、極楽ではただの糸だとしか思われていないと思うが、地獄では銀色の蜘蛛の糸と表現されている。これも大きな差だろう。極楽と地獄の共通点があるかと考えたが、共通点は見つからなかった。
私が罪を犯すか犯さないかでもし極楽と地獄に分かれてしまうのなら、もし分かれないとしても罪は何の得もなく、損しかない。次に私は蜘蛛の糸は蜘蛛の糸でも、蜘蛛の心の糸だと思った。
その理由は、カンダタの蜘蛛を助けるというとても優しい心にに対して、その糸は何人もの人はぶら下がっても切れない強い糸になったが、自分だけが地獄から抜け出し、自分一人だけが極楽に行こうとする、とても貧しい心がその蜘蛛の心の糸を弱い物にしてしまったから、蜘蛛の心の糸だと思ったのだ。
最後にこの作品はとても短い文章であったが、内容は深く、様々な考察ができる。この作品では人間の貧しい心や自分一人が得をしたいという醜さや罪人は上から見下され、天と地に分けられ差別されることが書いてあった。
作品を読み終わった時、テレビから流れていた犯罪のニュースを聞いて、「罪」とは何か考えさせられた。
(20代女性)
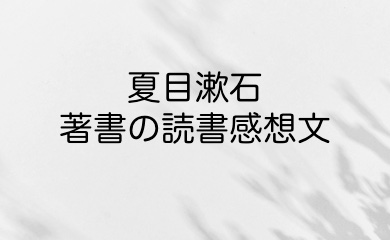
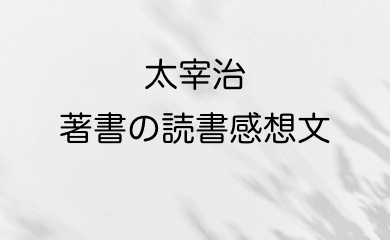
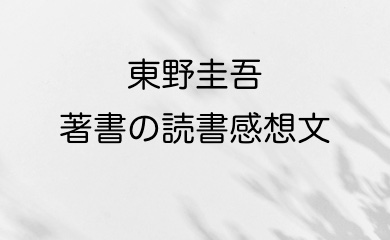
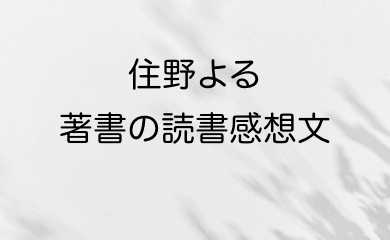






















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!