「行人」の読書感想文
この物語は新聞の連載小説という事でしたが、ヤマ場が二か所あるように感じました。兄・弟・嫂という関係である一郎・二郎・お直を中心に、その家族と友人の心の有り様とその絡み合いが描かれています。
一郎が、二郎に「それでは打ち明けるが、実は直の貞操をお前に試してもらいたいのだ」と言う所から、一家の旅先での何かが起こる感がどんどん膨らんでいきます。ドキドキ感も増して、そこには男と女という色の香りを想像させます。
しかし、単純な男女間の構造ではなく、一郎の異常といえるほどの思考回路が、関わる人全ての心情に影響を与えているのです。
二郎とお直が宿泊する羽目になった宿の部屋で、明かりが嵐の影響で突然消え、二人きりのその空間での出来事・会話のやり取りが最初のクライマックスです。
それから、その旅行から帰ってからそれぞれの登場人物の心の変化ともつれ合いは興味深く展開していくのですが、最後の章の「塵労」で一郎の精神分析を行うべく二郎に頼まれたH氏が、その旅行に連れ出すのに成功し、旅先からとてつもなく長い手紙を送ってきます。
その手紙の内容は最後の章の殆どを占めている量なのですが、一郎の精神状態を心理学的描写で宗教・神まで絡めて書き綴っています。その文体には迫力があり、漱石が自分の気持ちの内面と葛藤をぶちまけているんじゃないか思えるほどです。
それは漱石の心の告白でもあり、漱石自身執筆中は胃潰瘍とともに精神状態も極限まで達していて、書くことによりバランスを辛うじて保っていたのではないでしょうか。物語の構成としては最初の方と後の方とは文体を通して伝わってくる感触が違っていて、統一感がありません。
しかし、そのことが物語に、妙にリアルな迫力を与えているという事になっているのかもしれません。どちらのクライマックスが読み応えがあるのかは、人それぞれだと思いますが、私は最後のH氏からの手紙の部分にのめり込みました。
手紙の中に次のような一郎の言葉が出てきます。「何も考えてない人の顔が一番気高い」「絶対即ち相対」・「あれは僕の所有だ」・「目的と方便」等々。
言葉の持つ本質をくみ取るというか探ることは難解です。精神を病んでいる人の言動ととらえて読み流すのもありですが、あえてその言葉の発生の意味を考えて読むのも面白いと思います。
しかし、よくこんなリアルな言い回しを書くことが出来たなと思いました。当時は心理学の知識や臨床の情報等は今ほど出回っていなかったはずだからです。漱石自身がそういう精神状態に近かったのかもと、そして漱石の内なる言葉ではないのかと考えてしまいます。
人により感じ方が違うと思うのですが、自分なりに理解したというか感じ取ったのは以下の通りです。
「何も考えてない—-その顔が一番気高い」
全ての事に真理があり正解があるはずだ。だが考えても考えても確信をもてる真の答えにはたどり着かない、でもそこで思考を止めることが出来ずにさらに考え続ける。しかし、自分で認めたくはないが何も考えないことの方が考え続ける自分より優位にあるのでは。と考える一郎がいる。
「絶対即ち相対」
自分が考え抜いた心理が絶対である。その境地に達することができればそこには安心がある。そこに自分は到達したい。この考えは絶対なのだ。全ての物事の上に位置するのが絶対の真理。と何かにとり付かれたようにその真理にすがる一郎。
「あれは僕の所有だ」
唯一、自分の思い通りになる対象。信頼できる、決して裏切らない物。一郎が安心できる物。心を許せる物。しかし、悲しいかなそれは人ではない。一郎は人との交わりを持てない。他者が存在しない。H氏はそのことはつまり、物から支配されいるということでもあり、それが一郎の思考を上回る支配であるならば、思考の支配から一郎を切り離すことが出来るかもしれないと言う。
「目的と方便」
理屈が通ってない考えは自分にはできない。それをすることは苦しいH氏は目的がなくてもそれを行う事に意味があるのではないかと言うが、一郎は目的がない行いは意味がないという思考しか持ち合わせていない。
以上は読みながら頭に浮かんだことですが、物語との対話というか思考のキャッチボールを行いながら読むのも面白いのかなと思います。
「死ぬか気が違うか宗教に入るかしかない」という一郎の言葉がありますが、死ぬことも出来ず宗教にも入り込めないことを明かし、気が違う事しか今の苦しみから逃れる方法はないのだというのです。
完全に自分の思考を信じ切れるならまだ救われるのだけれど、自分を否定することも彼の思考の中にあるのです。一郎の思考回路は相反する回路を同時に所有しているので苦しむのです。
どちらか一つに統一できるか片方を切り離すことができれば楽なのですが。気が違うということは、まったく一つの考えが自分の頭を支配するという事になるのかもしれません。回りの人はそれが「きちがい」だということになるのでしょう。
題名の「行人」ですが、読み方はコウジンもしくはギョウニンと読めます。調べてみるとギョウニンとは修行僧という意味がありました。
一郎はまさしく「行人・ギョウニン」の人なのかもしれません。矛盾する考えを持ち合わせていて生きていく、しかもそれを追求することにとび抜けて明晰な思考回路を持っている。まさに、「死ぬか気が違うか宗教に入るかしかない」という結論に達してしまいます。
この手紙を読んでいてうすら寒い迫力を感じるのは、書いてる漱石が同じことを考え、悩みながら文面に向き合っているからではないでしょうか。これは漱石がこころの中の言葉を小説に書きなぐっているのです。
この小説の終わりの最後の行に書かれているH氏の言葉が、一郎の行人としての苦しい旅のことを憐れみをもって表現しています。
「兄さんがこの眠りから永久覚めなかったらさぞ幸福だろうという気がします。同時にもしこの眠りから永久覚めなかったらさぞ悲しいだろうという気もどこかでします」と。余韻の残る、物語の締めくくりの文章として凄く気持ちに残る言葉だと感じました。
この小説を私たちは当時とはすっかり変わった今の世の中に身を置いて読んでいます。明治のころとは違い、人はみな基本平等に生まれ、生き方も思想も自由でしかも飽和状態。
当時は知識人の悩みを描いた小説という位置付けだったのでしょうが。今は、知識人だけではなく誰もが一郎のように心の病とは隣り合わせの生き方を強いられます。
一郎の発する言葉のなかで「人間の不安は科学の発展からくる。・・・・」というのがありますが、文明開化の以前は人は汗水流して働き、その日を充実した気持ちで終わり明日につなげる。
あるいはそんな高等なこと考える余裕すらなく、生きていくので精一杯だった。ということなのかもしれません。そういうところから考えて見ると、一郎が文明の発達とともに人の不安も増えてくると言うのは理解できます。
当時の知識人といわれる人が、新聞を買ってどんなことを考えてその連載小説を読んでいたんでしょう。一言でいい現わすと、一郎の考えは他者不在なのです。一郎の考えの中に他人の気持ちは存在しません。それでは人と交わることはできないのです。
彼はまず最初に思考があり、その思考が完成しないと実際の行動には移せません。しかし、人の思いというものは、まず相手がいてその相手のこころに反応して自分の気持ちも変化・対応して行くものなので、いくら考えぬいても一郎の答えは正解ではありえないのです。
一郎の思考は欠陥があるのです。大事なものが大きく欠落しているとも言えます。結局、考え過ぎるのはよくないということなのでしょうか。
人は良くなろうとして色々な知識なり道徳なりを自分の中に取り入れようと努力するけれども、結局は本来持っている真っすぐで正直な気持ちには勝てないのかなと思いました。素晴らしいことをいう人よりも、自然体の自分をさらけ出している人が素晴らしいと思う時もあります。
しかしながら、過ちを修正し正しいことを学習していけるのも人間です。一郎のように考え過ぎないうちに終わりたいと思います。
(20代男性)
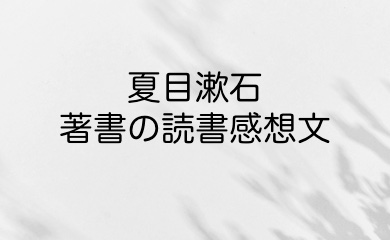
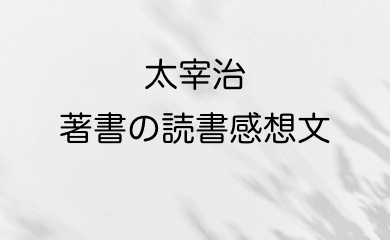
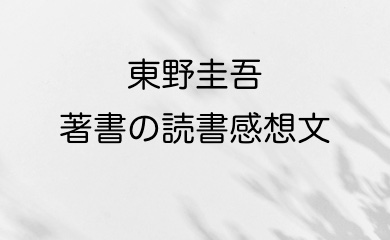
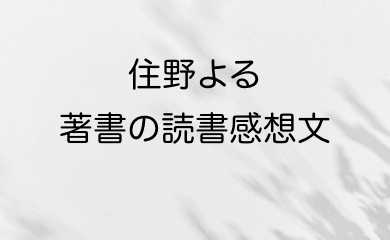





















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!