「まほろ駅前多田便利軒」の読書感想文①
「幸福は再生する」果たしてそうだろうか。小説の最後に書かれた一文を読んだ時、私は自分自身の生きてきた道を省みた。小説内では、不慮の事故で切り落とされた行天の指が再びくっついて再生する描写があった。だがもしも、切り落とされた指先がどこか遠くへ消えてしまったとしたらどうだろうか。
まるで尻尾を失ったトカゲのように、その指先が何事もなかったように生えてくることはないだろう。消え去った指の存在を惜しみながら、傷がふさがる頃には4本指の手の完成だ。私は生きた道程を振り返る時、そこで失ってしまった物たちの面影を探す。大切な人だったり、大切なものだったり。
もう戻らない「幸福」の欠片たちの残滓を、どこかへ見出せないかと躍起になる。小説内で多田が言うように、幸福は形を変えて私たちの前に現れるのかも知れない。だが私にとってそれは「再生」ではなく、ただの新しい出会いなのだ。過去に得た「幸福」は、これから出逢う「幸福」とはまた別のものである。消え去った指先がもう戻らないように、失ってしまった「幸福」だってこの手には戻らない。
だから私たちは、新たな日々の幸せや、あるいは今まで持っていた「幸福」に似た形をしたものを探すことで、心にぽっかりと空いてしまった空洞を埋めようとするのではないか。私は今から丁度4年前、親友を亡くした。彼女と過ごした日々は、とても充実していて笑顔にあふれたものだった。彼女がこの世を去った後、私は喪失感を抱えながら、それを埋める何かを探していた。
病院で手術を受ければ元に戻る指と違い、亡くなってしまった人間はどうやっても戻らない。また新たな友人をつくり、充実した日々を送ることも考えたが、やはり彼女以上に必要だと思える存在にはまだ出逢えていない。結局、私は諦めた。彼女の不在を認め、その寂しささえも受け入れることにした。
なくした指先を探すより、指先をなくした世界で何ができるかを考える。多田や行天のような運命的な出会いはないかも知れないけれど、大切な人を失った自分を乗せて、時間は確かに前へと進んでいく。きっと自分が思っていたよりも、世界は思ったよりも悪くないのかも知れない。爽やかな読後感に浸りながら、私は温かな熱を持つ自分の指先へそっと触れた。
(20代女性)
「まほろ駅前多田便利軒」の読書感想文②
人は誰でも孤独を抱えながら生きている。そんな当たり前のことを、私は『まほろ駅前多田便利軒』を読んでいて、ふと思い出す。二十代も後半になると、自分を取り巻く環境はひどく変わった。友達と遊ぶことは滅多になくなり、両親は結婚と金をせっつき、兄姉たちは健康だとか、姑とか、他人には手の差し伸べようのない問題を抱える。
休日の昼、誰もいない家でテレビを観ながら、心の中の私が叫ぶ。ああ、すごい寂しい! いい年こいて寂しいだなんて恥ずかしい。そう思いながら。そんなとき、『まほろ駅前多田便利軒』を読む。三浦しをんの作品は大体持っているけれど、思わず本作を手に取ってしまうのは、作者がこの作品で伝えたかった「空気」を感じ取ってしまうからかもしれない。
主人公の多田や行天は、周囲に少なからず友人や家族、知り合いが存在する。私は孤独というものについて、「一日で会話をする人がいるかどうか」を判断基準に置くが、そういった意味で多田や行天は別に孤独ではない。どうでもいい日常会話の話し相手がいるし、自分を知る人間がたくさん存在する。
便利屋などという浮世離れした仕事においても、多田は着々とこなしている。充実した人生を送っているようにも見えるだろう。だが、二人は、孤独なのだ。傍目から見れば十分に楽しそうな人生でも、辛い過去と永遠に失われた絆が、思い出したかのように多田を苛む。
行天は(作中では明らかにされないが)、幼少の家庭環境が彼の人格に大きな影響を与え、人との深い関わりを避けるようになった。彼らは互いに事情をそれとなく知りながら、慰めあうこともない。深く踏み込もうともしない。ただ漫然と日々を生きていく。
『まほろ駅前多田便利軒』を読み終えると、私はいつも胸のうちに、どうしようもない疼痛を覚えるのだ。多田と行天。架空の世界に生きる彼らもまた、孤独のなかに生きていると。主役二人だけではない。作中に登場する人物のほとんどがそうなのだ。言葉や態度だけでは詰め切れない関係性を抱き、ときには不満といら立ちを覚えながら、それでも生きている。
少し読み返そうと思っただけなのに、結局一冊全て読み終えてしまった私は、わずかに痛む目と頭をほぐしながら、安心する。孤独なのはきっと、私だけではない。そう思いながら、明日も生きていこうと思えるのだ。
(20代女性)
「まほろ駅前多田便利軒」の読書感想文③
愛情、とは何なのだろうか。私は幼い頃から、母親の思い通りに生きてきた。そうしなければ、「お前は私を愛していない」と言われていたからだ。愛情を示すためには、母親の言うことを聞き、意に反さない行動を取り続けるしかなかった。そんな私が結婚し、子供を産み母親となった。不健全な愛情しか知らない私が、自分の娘にちゃんと愛情を注げるのだろうか、そんな悩みを抱えながら育児をしていたとき。
私はこの本を読んだのだ。本書には、様々な境遇の人物が登場する。妻と離婚し、その傷を引きずる者。奔放そうに見えて芯があり、それを見せずに生きる者。親から関心を寄せられず、孤独を抱えながら犯罪に手を染めてしまう子供。その誰もが抱えている人生の課題のようなものが、「愛情」なのだと私は思う。
例えば「木」という単語を聞いたときに人はおおよそ同じものを想像することができるだろう。しかし「愛情」という言葉を聞いたときに想像するものは同じであろうか。答えは否だと私は思う。何故なら、人は自分が受け取ったことのあるものしか、「愛情」として認識出来ないからだ。
私自身にとって愛情とは長年、相手の思い通りになることだった。そして自分を愛してくれる人にも同様の物を求めた。それはとても苦しく、辛いものであった。幼い娘を前に、どう愛情を注げば良いかわからない。注いでいるつもりなのに、それが健全であるかそうでないのかわからずに不安になる。
こんな私は母親になってはいけなかったのではないか。他の人には話せない苦しみだった。まほろ駅前便利軒を読み進めていくと、こんな言葉に出会う。「愛情というのは与えるものではなく、愛したいという気持ちを相手からもらうこと」なんという重く美しい言葉だろうか。
この言葉に出会ったとき、私の目からは涙が流れた。1人で読んでいたにも関わらず、しゃくりあげて泣いた。苦しくてたまらなかった悩みから、解き放たれた瞬間であった。その瞬間まで、私は娘に愛情を「与えよう、与えなければ」と思っていた。
自分自身が十分に愛されてこなかったにも関わらず、無いものを振り絞って与えなければいけないと思っていたのだ。しかし本書を読み、それは少し違っていたと気が付いた。与えたいと思うことこそが愛情であったのだ。そしてその気持ちこそ、目の前の小さな小さな我が子が、私にくれたものだったのだ。
人に「与えよう」というのは時におこがましい。それは親であっても同様であった。私はまだこの世に生まれたばかりの小さな娘から、愛したいという気持ちをもらっていたのだ。本書を読み終えてから、私の心には変化が生まれた。愛さなければ、愛せているだろうかという不安はなくなり、娘と笑う時間が増えるようになった。
この言葉に出会わなければ、そしてこの本に出会わなければ、私はまだ誰にも言えぬ苦しみを抱えたまま育児をしていたことだろう。「愛情」とは何か。それは人によって様々な解釈があり、だからこそ人は苦しむ。そんなとき、この本を読んでみる。きっとどこかに自分に合った答えが見つかるのではないだろうか。
(20代女性)
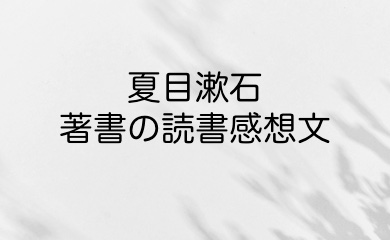
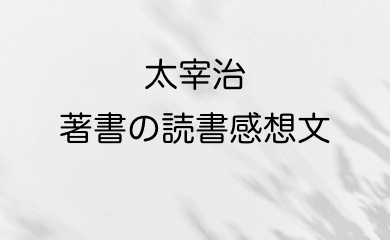
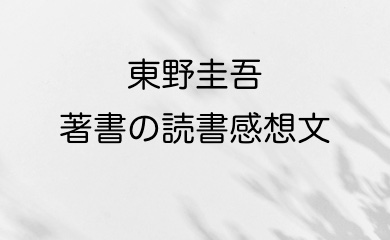
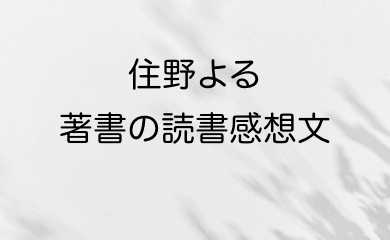



















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!