
「怒り」の読書感想文①
映画化されるということで作品を知ったが、あらすじが面白そうだっので映画公開まで待ちきれず、原作小説を読んでみた。この『怒り』という小説を読んで一番感じたのは、『人を信じれるか信じれないか』ということ。そこの表現がとても深かった。
簡単に人を信用できる人、疑う人、信じてたけど周りに流される人。信じたいけど、信じられない。信じてるけど、どこかで信じれない。少しの疑惑が人間関係を狂わせてしまうのが、もどかしくて胸が苦しくなった。
3つの土地で同時進行で話が進むのも、飽きっぽい私には常に新鮮で良かった。殺人犯の疑惑がある三人の男、どの人も怪しくてクセがある。私は最後の最後まで犯人が誰かわからなかった、むしろあの人が犯人で登場人物と同じように動揺し、ショックだった。
この人が犯人じゃなきゃいいのにと思ってたぐらい、今でもちょっと信じられない。裏の顔って隠せば分からないものなんだとつくづく思った。そして犯人がなぜ殺人を犯したのか、そこが小説で語られてなくさらっと終わってしまったのが残念。
『怒』の文字を殺人現場や住んでいた場所に残してあることから、犯人が『怒り』を抱えていたことは明白だ。犯人が殺人を犯すに至って家庭環境や生い立ちなどは書いてあったが、凶行に駆り立てる書籍のタイトルの『怒り』の部分が見えてこなかった。それにより感情移入や同情もできなかった。
殺人を犯す背景を知ることにより、どこか納得する部分があって読んだ満足感に駆られるものだが、それがなくて消化不良のような気分になった。しかし登場人物は全て魅力的だった。3つの土地で、3通りの愛のかたちがあった。
ハッピーエンドもあればバッドエンドもある。マイノリティや一般社会では生きにくい人達も描いていて、登場人物にイライラしたり、もどかしかったり、憧れたり、応援したり、素直に感情移入できた。
愛する人が、信じた人が殺人犯だったらどうする?というのがこの本のテーマなら、この本を読んだら簡単に信じちゃいけないのかな?と思うようになる。そんな人を信じることを、自分に問う作品だった。
(30代女性)
「怒り」の読書感想文②
書店でこの文庫を見たとき、映画化されるという帯がかかっていて、そこにそうそうたる俳優陣が並んでいた。それでこれは物凄く面白い小説なんじゃないかな、と思い読んだ。物語が終盤に差し掛かった時、ぞわわわっと身の毛がよだつようなシーンがある。その時に感じる嫌悪感は、人間が狂ったときにしでかす、何とも言えず気色の悪い行為に対するものだ。
ぬるい日常を送っているものには、よい刺激といえるかもしれない。 「怒り」、このタイトルに接して考えさせられるのは、「怒りとは何だろうか、それはどのような時に感じるものだろうか」ということだ。 この物語を読み終えて分かることは、それは「怒りとは、信頼を寄せたものに裏切られるときに最も強く感じられる」のだということである。
そのような時、人は相手を殺したいほどの衝動を感じる。それはきっと、自分の一番心の深いところ、一番大切にしている信条のようなものを、淡い期待とともに相手に捧げているからであろう。見返りを求めるつもりはなくとも、自分が捧げたような純情を、相手からも受け取るという幸福を、夢見ない人があるだろうか。 その真心を裏切られた時、自らの全存在が否定される。
そしてかすかな期待を寄せていた自分の気持ちに気付いた時、それは恥辱に変わってしまう。それら一連の心の動きは、まるで畳みかけるようにめくるめく展開し、一瞬にして愛すべき凡人を殺人鬼に変えるのだ。 主人公たちは、みな懸命に、良心をもって生きている若者たちだ。痛々しいほどの献身をもって、愛する人をかばおうとする者がいる、そして見知らぬ者同士が、孤独を分かち合い、慰め合おうとする。
しかし一点の黒い染みのように、狂気と憎悪にまみれた者の存在が、全ての歯車を狂わせていく。その憎悪は、良心を持った者の心にも憎悪を生んでしまうのである。愛や思いやりをもってしても、決して理解しあえない者たち。
救いようのない崩壊の中で、それでも若者たちは生きようとする。当たり前のようにそばに居ることはできなくなってしまった。でも遠く離れても決してお互いの存在は消えない、絶対に忘れることのできない相手…。悲しすぎる結末に、ほんの少しの希望を見いだせるかどうか、読者の感想はさまざまであろう。しかし人の心とは、とてつもなく闇深いものであることを突き付けられ、しばし呆然としてしまう読後である。
(40代女性)
「怒り」の読書感想文③
本作は映画化もされているそうだが私は見ていないし、吉田修一氏の作品を読むのもはじめてだった。友人との待ちわせの間、時間をつぶすべく本屋に寄って、なんとなく気になり、なんとなく読み始めた。そして一気に引き込まれ、一気に読み終わった。読み終わるころには人目もはばからず大粒の涙をこぼし、目の前が滲んでいる自分がいた。
本を読んで涙したのはかなり久しぶりだった。設定された3つの舞台は房総、東京、沖縄の離島。それぞれに事情を抱えた人々の前に、それぞれ謎の男が現れる。それぞれの舞台はあまりというか全くつながりを持たない。こういうパラレルワールド的な設定が構成としては面白い。
しかし私が心惹かれたのはそこではないのだ。この作品では「信じること」が一つのテーマになっている。家族を信じること、友人を信じること、自分を信じること。そして普段あまり意識はしないけれども、信じることはとても勇気のいる、時には辛いことであるということ。その辛さを乗り越えていくことが本当に信じるということであることを教えてくれるのだ。
時々不信が襲ってくる。何かを疑うという気持ちは、信じる心よりもずっと成長が早く、あっという間に育ってしまう。そして信じる心とはこれほど相手に伝わりにくいものかと歯がゆくなる一方で、疑いの気持ちはあっさりと見透かされてしまう。そこから生まれる軋轢、不和、そして破綻。読み進めていくにつれて、そんな過程がまざまざと見せつけられる。
もう一つは「居場所」ということだ。自分の居場所を見つけられる人間はなんと幸せかということが描かれていると思う。ほとんどの人間は多少の葛藤はありながらも自分の居場所を持っているのだ。それが当たり前のようになっているから、居場所のある幸福を感じない。しかしそれはとても稀有で感謝すべきことなのだ。本作はそんなことを思い出させてくれる。
絶望的なラストに疾走するかと思いきや、最後の最後で読者を救ってくれる終わり方は秀逸で、安心して本を置くことができた。本作を読んで涙がこぼれてきたのは、一つには自分には生きていく場所があることの嬉しさが込み上げてきたから、もう一つは自分を信じてくれる人たちの顔がいくつも浮かんできたからだ。
読み終わった後、年甲斐もないけれどすぐに母親に電話をした。何を言うわけではないけれども声が聞きたくなったのだ。電話口のそばにいた父とも二言三言、言葉を交わした。そもそも私の居場所を作り、何があっても信じる心を持ち続けてきてくれた二人に、照れくさいから言葉にはしないが心の中で「ありがとう」と言った。
(30代男性)
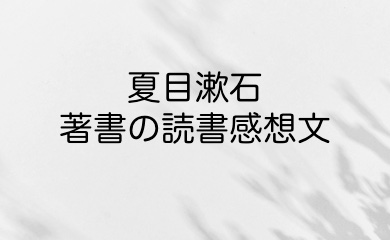
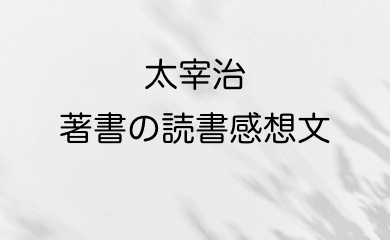
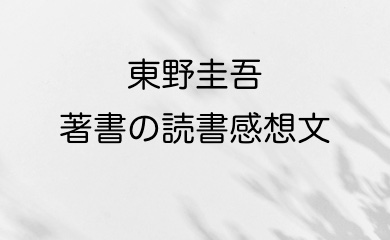
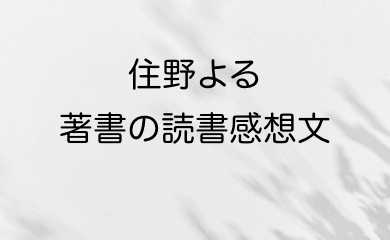
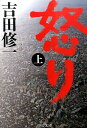















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!