
「放蕩記」の読書感想文
自分を産んだ母親を嫌悪し、更には憎むということを、人間の品格を欠く醜い行為、心情だと考えていた。しかし、その醜さを超えて初めて、母親を愛おしいと思えるのではないかと、新鮮な驚きを得た。そして同時に、「醜い行為」という言葉そのものを打ち消せる気持ちに、ふらつきながらも辿り着けたことに安堵した。
百組の母娘がいれば、百通りの親子関係がある。おそらく、似ていることはあっても、一つとして同じものはないだろう。人間は一人として同じ人が存在しないのだから。特に母娘に関しては、近年、友達親子や毒親なる呼称が知られることになった。うまく言い得ていると感心したものだ。わたしが娘だった頃は、もやもやした自分の気持ちに気づきながらも、いったいこれは何という感情なのかと思ったことがある。
小さな片田舎で、子供は親の庇護の下で安穏に暮らし、しかしながら、成人しても親が一番、絶対という風潮は否めなかった。25歳にもなった独身の娘がいるのは親の恥とでも言わんばかりの母親は、異常ではなく普通の人だった。隣近所への見栄や世間体を守るのに情熱をかける親はいくらでもいた。結婚どころか、進学校の高校を受ける、と言うだけで「女が大学へ行ってどうする」という親世代もいた。
わたしの今は、そういう親を超えられなかったことで成り立ってしまった後悔だらけの生活だ。しかし、それを親のせいにして、自分の弱さを直視したくない自分がいたのも事実だ。主人公の母親が、夫の不倫から受ける屈辱や怒りを、まだ女子高生の娘に話し、彼女を訳もなく叱責することで鬱憤を晴らそうとする。
ある日娘は、母親が押し入れの中に派手な下着を隠し持っているのを見てしまう。自分の有能さをひけらかし、傍目には優しい母親に映ることで、この人は懸命に自分を支えていたのではないだろうか。娘にしか自慢できない、自分の人生。何もなかったと思える人生を、しかし、母親自身は肯定できない。夫にも背かれる。
娘の心を傷つけることでしか、親の権威とも思える存在価値を感じられなかったのではないだろうか。かわいそう、と一言で押しやれない、その時代の生活もある。夫の価値観もある。わたしの母の昔を思い返してみても、この母親の行為に似たものはあった。わたしが一番嫌ったのは、親の恩を押し付けてくることだった。
父と諍いをすると、決まってこっそりとわたしの所へ来て、自分がいなくなってもいいのか、と囁いた。わたしは男兄弟に挟まれた一人娘だったから、必ずと言っていいほどわたしの元へ囁きに来た。「お母さんがいなくなってもいいのか?」と。同性だから、味方につけられると母は考えていたのだろうか。
わたしはどちらの味方もせず、ただただ、両親が仲良くすることだけを暗い部屋で祈っていた。けれど、恩をきせるのとは正反対に、わたしに手を出す、という行為をしたこともある。未成年の時も結婚話の時もだ。母は自分がかわいいだけなのだと思った。自分が敷いたレールに娘が反抗もせず生きていくことが自分の目的だと言わんばかりに。
母を憎んだ。しかし、憎み切れないのは当たり前だ。母だってにこやかに笑う日もあれば、父と仲のいい日もあり、わたしに抱きついて喜ぶ日もあった。結婚してからでさえ、習わしや近所づきあいで母が望むやり方を嫌だと口にできずに受け入れたことがある。わたしはどうしてこんなこともつっぱねられないのかと、自分の馬鹿さ加減を嘆いた。
そして同時に、母がこれで満足しているのなら、笑顔でいるのなら、これは親孝行という立派な行為なのだと自分を納得させたりもした。母を超えられない。母が偉大だから超えられない、などというのならどれほどよかっただろう。彼女の愚かな考えや行為に反吐を吐くような気持になっているくせに、拒絶できなかった、という意味だ。
父も含めて、両親の反対を押し切っての進学や結婚を、できないわけではなかったのに、聞き分けのいい娘のようにしか生きられなかったのは、全部わたしが悪い。それでも、親を憎むことで自分の後悔と折り合おうとした。しかし、親と音信不通になることは愚か、冷たい態度をとることさえできないでいた。
親も年を取り、自分さえ、嫌いだった頃の彼らの年齢を超えるようになってからは、そんなことも時効だと言うように自分の中では憎しみだった色も薄くなってはいった。年老いた親を見れば、昔とは違った愛情が湧くからだろう。親のせいでこんな人生になった、というのは逆恨みだし、お門違いだ。わたしは若かったし、親の不当な想いを跳ね返せなかったこと自体も、それこそが自分の人生の一部だと思う。
この中で、派手な下着を見つけた主人公は、母こそが不倫をし、父に対していい妻ではないのではないかと疑う場面がある。しかし、やがて父の口からは真逆の事実が語られる。そして娘は、母は苦しかったのだと、その心に想いを馳せる。だからと言って、親が子供につらく当っていい理由にはならないが、親とて弱い人間だということに何か場違いな新鮮さを感じた。
親は絶対の存在だった。仙人のように、生きているのだとさえ思えた。学生にもなり、自分が母親になってさえも、どこかでその気持ちはうごめいていた。打ち消したくてもできない。年老いてさえ、昔と同じ物言いでわたしに接する母を見ると、幼かった時と同じようにわたしもまた腹が立つ。憎め、汚い言葉をぶつけろ、と誰かが耳元で囁く。しかし、いつも苦笑して終わりだ。
母に、わたしはあんたのそこが大嫌いなのだ、と思い知らせたところで、自分はせいせいするのか、母に一矢報いることになるのか、それもわからない。笑っている母を見ていたい、というのも本当の気持ちだ。それが血というものだろうか。最終章で、認知症が進んだ母親との電話に、娘が苦笑しながらも涙する。
怖かった母親が、年老い、呆けて、小さくなっていく。その姿を受け入れて娘は尚、母を愛おしいと強く思う。憎んだ母の、その胎内から生まれ出て初めて成立した自分の存在は、わたしの中に彼女と同じ血が脈々と流れているということだ。醜さも同じように持っているのだ。わたしが母より聖人だと言える理由はない。
憎んだことは責められることでもないし、詫びることでもないと思えたことは、これから尚年老いていく母をまた別の目で優しく見られるのではないかと勇気を得た。
(60代女性)
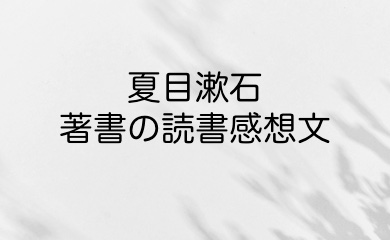
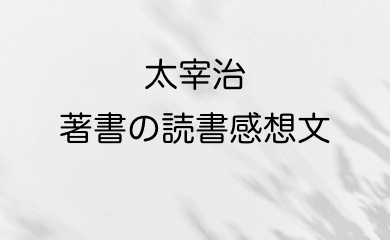
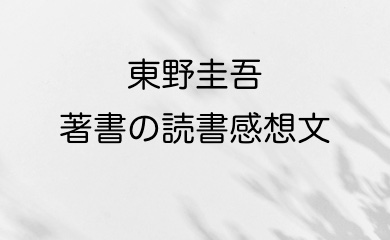
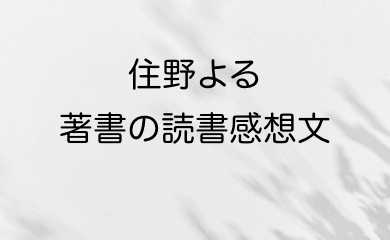













Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!