益田は、同期に入社し、同じ寮に入ることになった鈴木と親しくなるものの、彼がかつて世間をさわがせた「黒蛇神事件」の犯人ではないかと疑うようになる。そして彼はついに事実を知る、という話。この小説に関するレヴューなどをネットでみると、鈴木は本当に反省しているのだろうか、とか、彼はほんとうに更生したのだろうか。
あるいは更生できるのだろうか、とかいった鈴木本人に対する疑いの目と、自分は鈴木のような人間とは友達になれないとか、人を殺したことのある鈴木のような人間が自分の身近にいたら、自分は許せないという意見があまりにも多いことにぼくは驚く。人殺しを許せ、といいたいのではない。でも、少なくとも本を日常的に読む人たちからは、もっと違う、別の角度からの意見を聞きたかったからだ。これでは、一般の、傍観者と同じではないか。
そしてそれは、読者だけでなく、作中の登場人物たちにもいえることで、罪を犯した鈴木に救いはなく、物語を読み終えたとき、やるせない気持ち、後味の悪い気持ちで本を閉じることになる。被害者の気持を考えたら、罪を犯した人間を許すことはできない。罪を犯した人間が人生を楽しむなんてあってはならない。そういって、社会を構成する人たちのなかには、罪を犯した人をすでに法が裁いたのに、「被害者の感情」を考えたらを理由に、まだ裁き足りないといわんばかりにその人をさばく人たちがいる。
この小説は、こうした現実の社会を、そのままなぞったにすぎない。「被害者の感情」を考えたらを理由に、罪を犯した人にかかわる、一般の、法律関係者ではない人たちがする一種の制裁は、はたしてそれは正義なのだろうか? 被害者の気持ちというが、被害者はみな、社会がしようとしているようなかたちで加害者に制裁を加えたがっているのだろうか。もっと違う形――それを被害者自らは言葉にできないような何かが――もあるのではないか。
[google-ads]
どうやったら自分の過去と向き合えるのか、罪をつぐなえるのか、罪を犯した人に対して、他の人は、社会は、どうかかわればいいのか、人の罪をゆるすとはどういうことか、罪を犯した人が救われるとしたら、それはどんなことか、あるいは、罪を犯した人にはもう救いなどないのか……。この小説は、ものすごくいいテーマに取り込んでいながら、こうした疑問に対して不十分なまま終わってしまっている。
残念でならない。鈴木だけでなく、同僚の益田にしろ、事務員の美代子にしろ、寮長の山下さんにしろ、暗い、重い過去を引きずって今日まできている。このように重いものを背負った人たち――弱い人の立場や気持ちが、そうでない人よりもわかりそうな人たち――がいながら、鈴木にとってのほんとうの味方・理解者は一人もいない。まるで自分は鈴木――人を残酷な仕方で殺した鈴木――とは違う、と思っているようだ。
はたしてほんとうにそう自信をもっていえる強い人は存在するのだろうか、とぼくは思う。ぼくは人殺しにならないと断言する自信はない。それは今まで誰かに対して殺意をもったことがあるからではない。自分が弱い人間だと思っているからだ。たとえば、戦争が始まれば、ぼくは兵隊に行くだろう。戦争をいいことだとはちっとも思っていないのに、だ。そして何の恨みもない、昨日までぼくとは何のかかわりもなかった相手の国の誰かを殺すのだろう。だからぼくは鈴木を裁けない。
だが、小説では、現実の社会同様、犯罪をおかした鈴木を、全員が、まるで、警察か検察、裁判官かのように裁くのだ。そう、ジャン・ヴァルジャンに対してふるまった、ジャヴェールや町の人々のように。この小説には、たとえば「レ・ミゼラブル」に出てくるミリエル神父のような人は存在しない。もしもジャン・ヴァルジャンが、ミリエル神父と出会わなければどうなっていただろうか。
ミリエル神父は、もと徒刑囚だったジャン・ヴァルジャンにどう接しただろうか。なぜ、ジャン・ヴァルジャンは、すでに自分の暗い過去も封印し、マドレーヌ市長になり、地位も名誉も財産も手にしていたにもかかわらず、シャンマチウ事件では、全てを失うことになるかもしれない危険をおかしてまで、ジャン・ヴァルジャンだと誤解されたシャンマチウに代わって、自分こそが本人であると名乗り出たのだろうか。
なぜジャン・ヴァルジャンは、自分をしつこく疑いの目で追うジャヴェールに対し、実力行使する機会がありながらそれをしなかったのか。なぜ彼は、フォーシュルバン爺さんが馬車の下敷きになったとき、それを見ていたジャヴェールが、下敷きになった爺さんを救い出せる怪力の男をわたしは一人だけ知っている、と言ったにもかかわらず、身を挺して馬車の下にもぐりこみ、フォーシュルバン爺さんを助け出したのか。
なぜ、ジャン・ヴァルジャンは、自分とは血のつながりもないコゼットを守り、育てたのか。過去に犯した犯罪のために鈴木を裁くみんなの姿を描くだけなら、それは現実を描いたにすぎない。この小説のなかで、鈴木に救いはない。人をゆるすとか、愛によって罪をおおう、そういう視点、そんな場面が一つでもあればよかったのに、と思う。
それでも、、この小説が、救いはないものの、「人を裁く、とはどういうことなのか」、「つぐないとか更生するってどういうことなのか」、「罪と罰とは?」、「加害者、被害者がこの社会でいきていくにはどうすればいいのか」、といったことを、読者に考えさせる機会を与えていることはたしかである。罪を犯した人と、ぼくらは、どんなかたちでかかわりあうようになるかわからない世の中に生きている。
ぼくらは、いつ自分が加害者、あるいは被害者になるかもわからない。裁判員制度によって、裁く立場になることもある。だからこそ、罪というものについて、今一度立ち止まって考える機会を与えてくれたこの本を一人でも多くの人が読んで、そして考えてほしい、と思った。
(50代男性)
[sc name=”post-under-massage”]
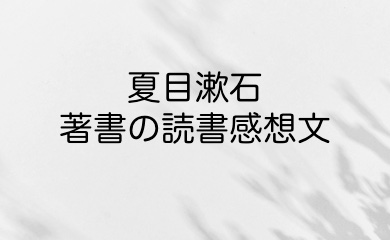
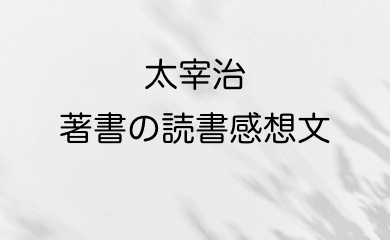
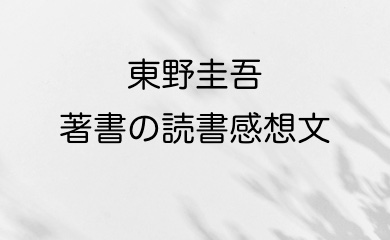
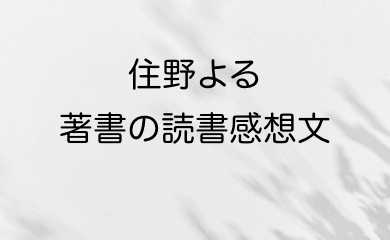












Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!