小説を読み終えたとき、ぐったりとしながらパタンと本を閉じ、深呼吸のひとつでもしたくなることがあるのは、ずっと同じ姿勢をとり続けていたためだけではなく、文字だけを頼りにしてそこに描かれた世界を頭のなかに立ち上げる作業が、想像力を酷使するからだ。
つまりそれを読んでいる最中、ひらたくいえば頭ははっきりしているのが普通なのであって、とはいえそれが良い読書の条件であるとあながち言いがたいのは、本書『梅崎春生(ちくま日本文学全集)』(ちくま文庫)に収録された「春の月」が読む者を、ひどくだらだらとした気分にさせるに違いないからだ。
[google-ads]
「戦後派」と呼ばれた梅崎春生の小説はおおむねふたつのタイプにわけることができる。ひとつは「桜島」に代表される、戦中における兵士の極限状況を描いた作品群だ。もうひとつは直木賞を受賞した「ボロ家の春秋」に代表される、戦後日本の市井の人々の生活をユーモラスに描いた作品群で、「春の月」はこちらに入る。
物語はあってないようなもので、10人前後の登場人物が入れ替わり立ち替わり、ある人物を追ったかと思えば、その横を通り過ぎた人物に視点が移り、といった具合に、それらの人々の体験した、それほど長くはなく劇的でもない出来事がひとまとまりとなって小説を形成している。はっきりした輪郭を持たない春の月のようにおぼろげに、しかしたしかな存在感を放って。
なにか特殊な磁場でも働いているのだろうか、出てくる者らは総じてだらだらしている。なかには深刻な問題を抱えている者もいるが、にもかかわらず気がつくとその緊張感はいつのまにか脱臼している。物語のなかば、勤めている会社が潰れかかっている男が登場する。男の悩みは深刻だ。なんせ月給が未払いで、子供と約束した玩具を買ってくることさえできない。
景気付けに、男の家に下宿している憂鬱症の青年が薬局で買った怪しげな「元気が出る貴重薬」をわけてもらい、なんの疑いもなく服用する。この選択も実に脱力的だが、問題は翌朝だ。憂鬱症の青年が、男にたずねる。「(前略)昨夜の薬は利いたかい?」「そうだねえ。よく眠れたよ。まだ眠いぐらいだよ。飯食ったらまた寝ようと思ってるんだ」
いますぐ医者に行けよ、と思う。「元気が出る貴重薬」を飲んで過剰な眠気を感じるのは、いかにも危険な状態だ。しかし、ここで病院に行くという解決を与える人物を登場させないところが、梅崎春生のシニカルな優しさのひとつの形だと思うのだ。なるようにしかならないときは、だらだらするものなのだ、とでもいうような。
ここにあるのは「桜島」のような極度に緊張感のある作品を書いた著者の出現させる「極度にだらだらとした場」だ。生半可な脱力感ではない。このだらだらには、力がある。
(20代男性)
[sc name=”post-under-massage”]
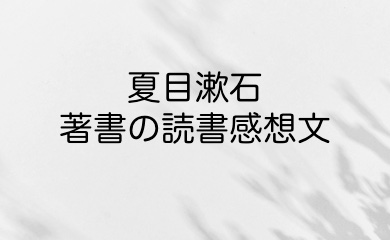
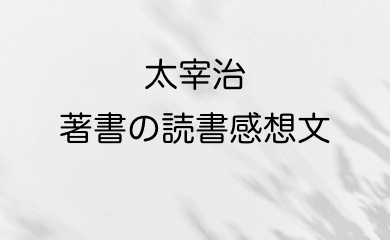
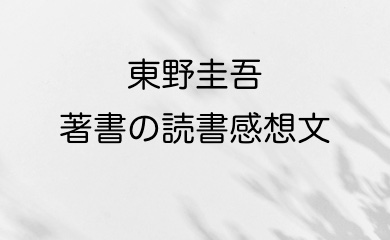
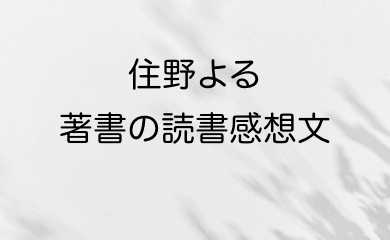













Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!