「時は永遠の旅人である。したがって時が歩みを刻む人生は、旅そのものであるといえる」これがこの書の主題である。「古典に親しめ」との恩師の言葉を思い出し、最近は中国や日本の古典を中心に読み進めている。
「奥の細道」は高校の教科書で学習した以外は深く読んだことが無かったが、退職を迎え新たな人生への旅立ちに当たり読んでみようと決意したものである。冒頭の主題は、高校で暗礁させられた有名な部分である。その時は水の流れだけを想起してたいたが、今この年齢になるとなるほどと深くうなずける。
ちょうど退職の3月に読み始め、6月初めに読み終わった。芭蕉の旅は深川を3月17日に出発し、旅の終わりは8月下旬岐阜大垣である。私の人生の節目の旅とも重なり一節一節を感動しながら読んだ。発句となる「草の戸も住み替はる代ぞ雛の家」は、今まで勤めた私の席に新しい住人が来て新たな仕事を始める事を思い、一抹の寂しさを感じさせてくれた。
[google-ads]
書店で偶然目が止まり購入した一冊だったが、これほど私の心情と合うとは思ってもみなかった。有名な「行く春や鳥啼き魚の目は涙」も退職の送別会とちょうど重なり、勤めた30数年間の思いと出会った人たちの事が思い起こされ、全てが涙に濡れるような感じだった。
さて、奥の細道は実際のままを記したのではなく、芭蕉のち密に練られた構成の元に書き表された紀行文であると知った。実際の旅の様子は、随行した曾良の随行記の方が正しいようだ。世に有名な「松島やああ松島や松島や」は観光用に作られたコピーであり芭蕉が作った松島の句は全く違い、「荒海や佐渡に横たう天の川」の実際は嵐で見えなかったという。
そんなエピソードも知ることが出来、楽しく読み進めることが出来た。終着大垣に至った芭蕉は休む間もなく次の旅を歩み始める。その時の句が「蛤のふたみに別れ行く秋ぞ」である。出発の句が「行く春」だったが、奥の細道最後の句は「行く秋」。この部分を芭蕉は意図的に構成したと解説されていて、奥の深さに一番感動した部分だった。
私の人生の旅も芭蕉のように深く生きる人生でありたいと願っている。
(60代男性)
[sc name=”post-under-massage”]
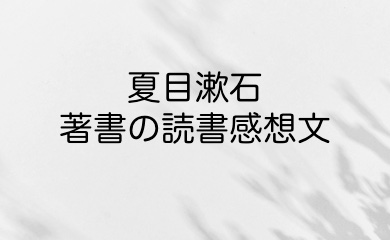
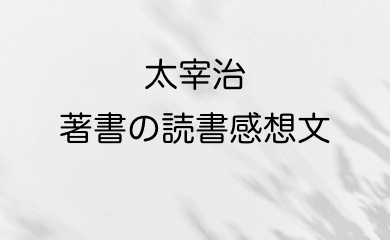
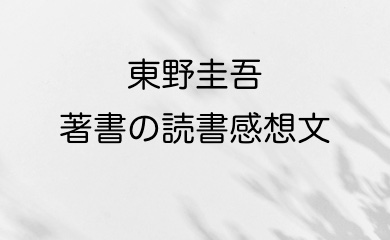
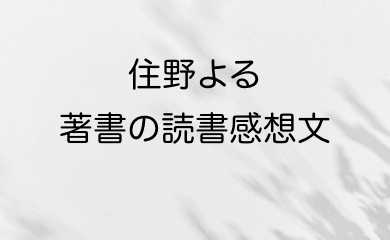












Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!