
「ぶらんこ乗り」の読書感想文
「愛しい」という気持ちでいっぱいになる本である。「愛しい」という言葉は帯にも記されていた言葉で、おそらく非常に有りがちな感情なのだろう。だが読後の気持ちは、どうしようもなくその言葉が一番しっくりきた。
読めば読むほど、登場人物たちが、言葉の一つ一つが、そしてこの本そのものが、愛しくてたまらなくなった。誰かや何かを理由もなくただ「愛しい」と思う気持ち、そういう何かがそばにいてくれること、そばではなくても在ってくれること、決して現実的とは言えない物語を読んでいく中で、私は確かに、非常にリアルに、そういうものの大切さを痛感した。
主人公であり語り手である高校生の私(姉)が、今はいなくなってしまったあの子(弟)の使っていたノートが出てきたことをきっかけに、弟のことを中心に幼い頃の自分や家族のことを回想するという形で進んでいく。回想の中の主体となる弟は、小学校で得意のぶらんこに乗っている最中、喉に雹がぶつかりを声が出せなくなる。出せないというよりは、出すことをやめる。それは「聞いた人が吐いてしまうほど」の声になってしまったからである。
声を失った弟は、自宅にある木の上のぶらんこで、寝起きを含め主な生活をするようになったり、動物と話せるようになったり、以前から少し変わった少年ではあったものの、さらに不思議な部分が多くなる。そうして、得意の作り話に、動物たちから聞いた話を織り交ぜてノートに書き連ねては、姉に見せていた。姉はその物語も弟も大好きで、弟も物語を見せて姉が笑ってくれるのが何よりの喜びになるくらいに、姉が大好きである。そのことが作中に明記されているわけではないのだが、読めば読むほど、ひしひしと感じて、それがこの本を愛しいと思える一つの大きな要因になる。
声を失う事件から、少しずつ変化し始めていた姉弟の世界は、旅先での事故で両親を亡くしたことを機に、さらに大きく変化してしまう。変化するというより、日常が崩れていってしまうと言った方が良いかもしれない。特に姉は絶望し、そう書かれているわけではないが壊れてかけている感じだった。弟ももちろんショックを受けていたが、絶望よりも姉の気持ちを助けたい気持ちが強かったのだと思う。
弟は両親を装おって姉にハガキを書く。だがその一通をきっかけに何故か両親が事故の前に旅先で家宛に書いていたハガキがぞくぞくと届き出したのである。ここは解釈が分かれる所だと思うのだが、私は一通目以降はおそらく本当に、どこからともなく奇跡的に届き出したのだと思う。この出来事は非常に悲しい部分ではあったのだが、重い言葉や表現はされていないのに、命や生きていることについて深く考えさせられ、そして、何より弟の姉を思う気持ち・親が子をを思う気持ちを深く感じ、胸が熱くなった。
作中でよく「こちら側」と「あちら側」という言葉が出てきた。これは主に声を失った後くらいから弟が使い出した言葉で、それがどこなのか・何なのか等、その言葉以上のことは語られていない。しかし、この本においてとても重要な言葉で、この捉え方によって、この物語の感じ方がだいぶ変わるように思う。
弟はよく自分は「こちら側」と「あちら側」を行き来しているかのようなことを、なんとなくだが匂わせているし、読んでいくうちにだんだんそうなんだろうなと、本当にぼんやりなのだが思う。そして、結末に触れてしまうが、弟は結果的におそらく「あちら側」に行く。
それから、両親のハガキのことに関しては、後に姉の言葉で、弟が精一杯の力で「あちら側」から呼び寄せたというように表されている。その言い方からしても「こちら側」は「この世」「あちら側」は「あの世」と取れるだろうし、実際言わんとしていることはそうなのかもしれない。ただ自分はそうではないと感じた。そうではないというより、そうでもあるのだろうし、それ以外でもあるのではないかと思った。
それが”何か”というよりは、人と人や、それに限らず何かと何かの間を明確に隔てるものというか、言葉で表し辛いのだが、絶対に接触することができない二つの世界のような、言葉は「こちら側」「あちら側」だけだが、そういうもの全ても含めた広い言い方なのではないかなと私は考えている。
「こちら側」にいるものは「あちら側」にいるものに触れることはできず、その逆も同じで、完全にどちらかの世界に行ってしまえばしまうほど、そうなるのではないかと思う。そのため、弟は、不思議な出来事で声を失った頃から物語終盤まで、双方を行き来している状態で、おそらくぶらんこで生活するようになったのは、ぶらんこの揺れに行き来する自分を重ねていたか、はたまた実際にぶらんこで行き来していたのだと思う。
そしてその弟は、必死に「こちら側」にしがみつこうとしていたように私には見えた。動物と話す等、明らかに常人ではない変化を見せ、おそらく「あちら側」を確かに感じながら、弟がノートに記した物語は、平仮名が多いこともあり一見ユーモア溢れた子どもらしくもある空想の物語なのだが、その一つ一つから、妙にリアルな痛みを感じる。それは一つの物語として、切なかったりヒヤッとしたり、優しい話であったりするからということもあるが、それだけではない。
何と言うか、とても直感的な、自分の根元の方にある感覚を、優しく優しくだが突かれるような、忘れていた或いは忘れようとしていた気持ちを少しずつ掘り返されるような、そんな感覚の痛みを感じる。一見作中一番現実離れして見える弟の言葉や作る話、そこから伝わる気持ちに、私は妙に共感してしまった。
私は時折、抗いようのない「孤独」を漠然と、だが明確に感じることがある。弟も、そういう部分があるように感じたのだ。弟は、いたずら好きであったり子どもらしい面も多く、決して引き込もった性格ではないし、温かい家族にも囲まれている。そして、作中では姉に対して強く表れているが、それら周りの人々を他に代えようのない大切な存在であると考えていて、特に姉に対しては、それと繋がっていないと自分でいられないくらいに思っているように感じる。
でも同時に胸の奥底に消せない孤独がある。それはきっと、どうしようもなく大切な存在だと思える存在があるからかそなのだ。私も幼馴染みの友人たちと関わる中で「この存在がなければ自分でいられないや」と感じる瞬間があり、家族はもちろん唯一無二なのだが、その瞬間から、そういった存在をより大切に感じるようになった。そして同時に、今までにない孤独を感じるようにもなった。
きっとそれは大切ならば大切なほど仕方のないことなのだと思う。私は永遠のものなどないと考えている。だからこそ、大切なほど怖く、独りというものを隣合わせに感じてしまうのだ。弟の作り話の中に、空中ぶらんこに乗る夫婦の話がある。「私たちは永遠に手を繋いでいることはできないのね」という奥さんに、旦那さんは「空中ぶらんこだからね。でもこうやってその瞬間だけでも命懸けで手を繋いでいられるかとは素敵なんじゃないかな」というようなことを言う。
まさに、これがそういうことなのではないかと、ハッとした。どんなに大切で大好きでも、永遠に手は繋げない、そばにはいられない。怖くて寂しいけれど、だからこそ、そばにいられる瞬間、いることができるときが大切で愛しくて、素敵なのだ。弟の存在だけでなく、今まで記しただけでもそうだが、この本の物語そのものが、全体を通してとても現実には考えられない部分も多い。
出来事はもちろん、姉の語りであることと、作中に弟の作り話が多く含まれているためもあってか、童話のような、ファンタジーのような、そんな世界観にも感じる。登場人物たちは少し変わっている人物が多いというか、全員どこかしら浮世離れしているように見える。それでも自分には妙に現実と重ねて考えてしまう部分があったのは、妙にリアルに痛いくらいに胸にきて、時に目頭が熱くなったのは、ふんわりとした世界や曖昧な言葉の中に、人間だけでなく動物や作り話の登場人物含め、皆痛いほど誰かや何かを思っていたからだと思う。
その気持ちは切ないほど、いつかは死んでしまったり、そうとは言わずとも別れがくるのだということを含め、生きているということを強く感じ考えさせられる。この本のおかげで、強く大切に思える存在がいてくれることの大切さや、それが当たり前ではない、奇跡といえるようなものなのだと改めて考えることができた。そして、一緒にいられる時間を、一秒も無駄にしたと感じないように大切にしたいと感じた。
その上で、別れが来ても、死んでしまったとしても、その何かを思うことはできる。何があったとして、思い出などではなく確かに大切な存在は大切なのだという気持ちを持ち続けたいと、この本を読んで強く思った。そして同時に、その大切だと感じる気持ちの愛しさを読めば読むほど噛み締める。これからも何度も読み返して、この気持ちでいっぱいになりたい。
(20代女性)
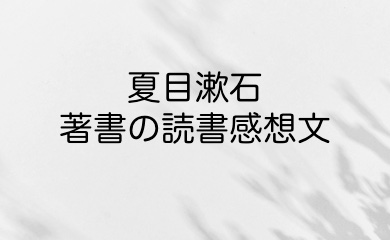
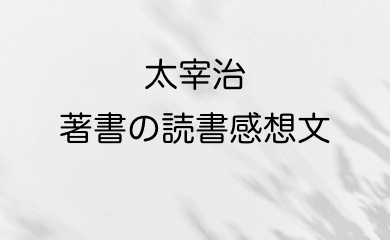
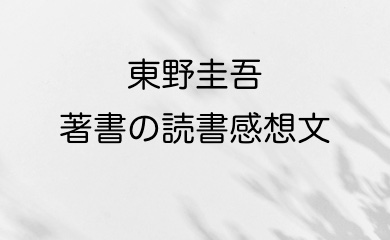
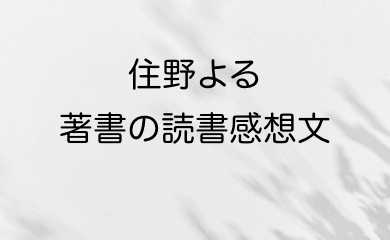














言い値