近年様々な場面で使用されている「空気」とは何なのか、という問いに対する一つの答えを日本語自体の話法や関係性という点から示しており、様々な気づきを得ることができた。近年様々な場面で使用されている「空気」とは何なのか、という問いに対する一つの答えを日本語自体の話法や関係性という点から示しており、様々な気づきを得ることができた。
近年、日本社会では「空気」の存在が公になり、政治や教育、ビジネスなど様々な場面で弊害を引き起こしている。一昔前に話題になった「KY」という言葉は、人々に対して見えない「空気」による同調圧力に従うよう求めており、それは情報や価値観を共有できない人にとって多大なストレスとなっている。
また近頃話題になっている「忖度」が引き起こした政治問題などを見るにつけても、日本の社会においては「空気」というものが大きな存在を占め、人々は「空気」に対してただ流されるだけで抗うことはできていない。そのような状況で、一日本人として「空気」にどう向き合い、どのように付き合っていけばよいのだろうか。
[google-ads]
この“「関係の空気」「場の空気」”という書籍では、「空気」の形成に日本語ならではの問題点が絡んでいる、と喝破し、「空気」にとは何なのか、どのように向き合っていけばよいのかということを日本語話法の観点から説明している。この本では、日本人同士の会話における「空気」を分類し、二人以下のコミュニケーションの時は「関係の空気」、三人以上のときは「場の空気」と呼んで区別をしている。
その分類には私も納得が行くし、現在の日本では「関係の空気」が希薄化し窒息していく一方で、「場の空気」は以前より猛威を振るうようになった、という指摘も妥当だと思う。私個人は「関係の空気」のもとで二人以下の友人と話すときは非常に饒舌になるが、三人以上、特に大人数の「場」となるとあまり多くは話せない。
この書籍でも、同じ価値観や情報を共有していないと「空気」を読むことは難しく、「空気」を読める人と読めない人との断絶が生まれやすくなるという指摘もあるが、まさにその通りである。あまりFacebookもTwitterも見ないし、噂話も飲み会もあまり参加しない主義なので、三人以上の「場」においてはあまり「空気」が読めない方だと思う。
周りに留学経験者が多いこともあってそんなに「空気」による同調圧力は高くないためあまり困っていないが、今後社会に出ていくにあたっては、この本で指摘されているような会社での「空気」の無言の圧力は重荷になるであろうと思うと少々憂鬱である。
また、この本においては日本語の特徴である省略やコードスイッチ話法(丁寧語とため口をまぜこぜにする話法)、隠語など様々な「私的空間での日本語」を、権力者が会社や政治など公の場に持ち出してしまったことこそが、公共の「場」が「空気」に支配されるようになった原因であると述べている。
その指摘は自分にとっては非常に痛いところを突かれたと感じた。実際、自分はこれまで後輩の立場であればしっかり敬語を使って先輩と話していたが、いざ上の立場に立つとかなりコードスイッチ話法を使ってしまっていた。無意識のうちに出会っても、自分の持つ「空気」が後輩にとっては圧力となっていたのだろうか、と思うと後悔の念を感じてしまう。
たとえ上の立場になろうとも、敬語を使うことで部下や後輩と適切な距離感を取り、対等性を保つというのは一つの手法としてはありだと思う。ただ、大切なのは言葉の使い方だけでなく、後輩や部下の気持ちや意見を尊重しようという意思や、自らで何が正しいのかを見極める慧眼であると考えているので、敬語などの言葉の使い方はもちろんそれ以外のものも鍛えていきたい。
(20代女性)
講談社
売り上げランキング: 281,381
[sc name=”post-under-massage”]
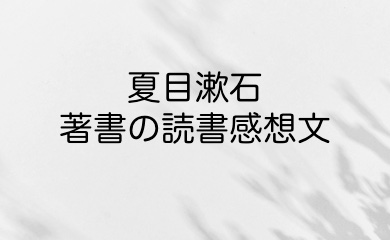
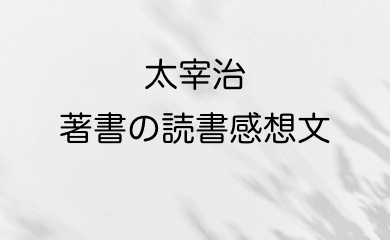
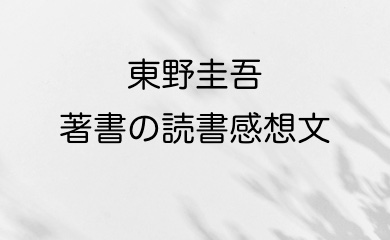
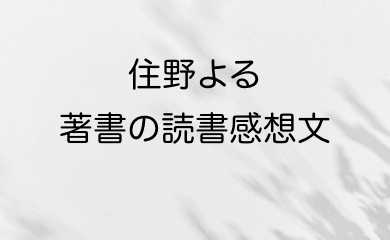












Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!