ステファン・ツヴァイクの伝記の代表作品「マリー・アントワネット」(上・下巻)。大学時代に一度読んで以来、最近再びこの本を読んだ。以前感じられなかったことが40近くなったわたしが再度読み返すことで、またさらに深く新たな感動を覚えたのは驚きだった。
歴史的には有能な人物ではなく、踊りや賭博に興じ国費を浪費した「赤字夫人」としての印象が強い面もあるが、ツヴァイクは一般的なマリー・アントワネットのそのような一面だけでなく、彼女の人間的な性質を深く描いている。
オーストリアのハプスブルク家から、政略結婚によりフランスのブルボン家に嫁ぎ、ルイ15世の崩御により、夫ルイ16世が即位し王太子妃から王妃となる。彼女の浪費はかさみ、時代は王政から共和制へフランス革命の流れによって、王一家はヴェルサイユからパリへ。逃亡も失敗し、やがて幽閉され、最後はギロチンにより死刑に処される王妃。
王妃としての気高さを持ちながらも、ひとりの人間、女として素直に自由を求めていた王妃。ダンスも遊びも、おしゃれも、また恋もしたい。現代の年頃の女性が求めることを、王妃であるマリー・アントワネットも求めていた。
これほど時代的にも、また環境や境遇がかわる人生を送ることになった王妃がいただろうか?また同時にそのような激動のなかで、わたしは彼女の性質や心の姿勢が変っていくさまを読みながら見守っている感じだった。
民衆の気持や国家の予算などを考えるに適性があった人物とは思えないが、ひとりの女性としてフランス革命の流れにさからうことはできずとも、最後自分に与えられた死……。それに対し、ただ毅然と受け止め死に立ち向っていくさまは、ひとりの人間としての彼女に対して、ただただ敬意をもたざるを得ない。
もともと王家の生まれであり、フランスに嫁いで豪奢な王宮に住んでいたマリー・アントワネットが、一転タンプルからコンシエルジュリで幽閉、監視される生活へ。夫ルイ16世は先に断頭台の露と消え、子供たちとも引き離される。
彼女の恋人と言われたスウェーデンの貴族、ハンス・アクセル・フォン・フェルセンもいない。おしゃべりやにぎやかなことが好きだった王妃が、孤独のなかで向かうのはただ死あるのみ。死に立ち向うのみ。
ファッションリーダーのような華やかな存在だったマリー・アントワネットは、見る影もない。白髪頭になり、劣悪な環境のなかで下半身から出血しまつだった。女性としても華やかさを失った、あわれな女性として感じるだろうか。豪華な馬車で移動していた彼女が、木でできた粗末な荷台でガタゴトと運ばれる姿を落ちぶれた、みじめな姿としてみるだろうか。
[google-ads]
わたしは処刑される直前のマリー・アントワネットの描写がありありと描かれるのを読むにつれ、外見や表面的なことよりももっと奥深くから感じられてくる、人間としての真の姿を彼女から感じずにはいられなかった。死ぬときにひとが、何を持っていけるだろうか。財産も名誉も死の前では無意味である。裸そのもので、真にひとりの人間として死にのぞむときはシンプルそのものではないか?と。
マリー・アントワネットの死にのぞむ姿に、わたしは環境、境遇などをこえて、ひとりの人間としたの尊厳を失うことなく、堂々と死に立ち向ってすすんでいく姿をみた。またその姿に対し、人間としての崇高さ、美しさすら感じられたのだ。
彼女がフランス革命の流れになかったら、裁判で死刑となりギロチン処されるということがなければ、彼女はこのように潔く死にのぞむ人間にはなりえなかっただろう。またこれほどまでに、深く静かに感動をあたえることも、なかっただろう。
(30代女性)
[amazonjs asin=”4042082076″ locale=”JP” title=”マリー・アントワネット 上 (角川文庫)”]
[sc:post-under-massage ]
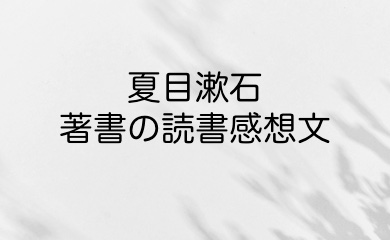
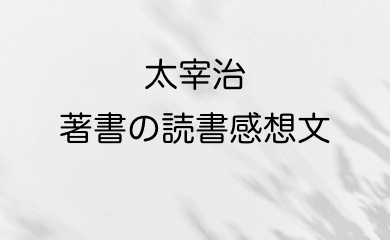
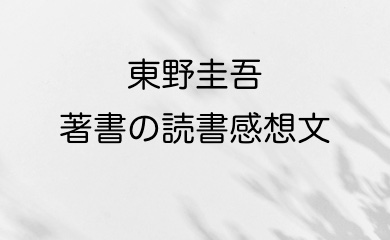
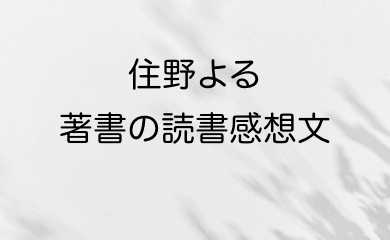













笑