「人魚の眠る家」の読書感想文①
この世には狂ってでも守らなきゃいけないものがある。そして子どものために狂えるのは母親だけである。これは、6才の愛する我が子が脳死になり、その子のためにできうる限りのことをした母親のセリフである。
親はいつだって子どもの幸せを願うものである。それは、子どもが脳死になってもそうである。脳死は人の死か。もし愛する我が子が脳死になれば、自分は子どもの臓器提供にイエスと言えるだろうか。現在の日本の法律では、脳死になった場合2つの死を選べる。
脳死である場合、意識が戻ってくることはない。心臓が止まるまで、延命措置を行い、心臓死を待つか、脳死判定を行い臓器移植に協力するかのどちらかである。
自分だったら、子どもの臓器提供に協力するとは言えないのではないかなと思う。子どもの心臓は動いており、寝ているような我が子をみれば、なかなか協力します、とは言えないと思う。
この物語のなかでも、子どもの両親は、迷った末、延命措置をとる。そして、彼らは脳死の我が子に対して、コンピューターを使い自分で呼吸させるのである。さらに、機械を使い筋肉を動かすトレーニングをさせるのである。
それに対して、周囲からは避難する意見もある。母親の自己満足ではないかという声もある。けれど彼女は譲らない。子どもにできうる限りのことをしてあげたいという。
しかし、一方でその母親は、臓器移植を望んでいる子どもとその親や支援者にも出会い、意見を聞く。そしてまた、自分が正しいことをしているのか悩む。どちらの両親も、我が子のことを一番に思いながらも、相手のことも思いやっている気持ちが伝わってきた。
親であれば、子どもが一番である。けれど、こんな辛い状況で我が子だけでなく、周りのことも思いやれるというのは、すごいことなのではないかと思った。
3年という長い間、子どもにできうる限りをした両親は、最終的に、子どもの脳死判定を受け、臓器提供を行う。それもまた、驚くべき決断であるが、彼らにとっては、悩んで、最善を尽くした結果のことである。
子どもが脳死になった場合、考えたこともなければ、考えたくもない。ほとんどの親がそうであると思う。けれど、それは突然やってくる。そして、突然決断を迫られる。
親はいつでも子どもの幸せを考える。子どもにとってどうしたが最善のことか、本当に深く考えさせられた本である。
(30代女性)
「人魚の眠る家」の読書感想文②
「母親は子供ためなら狂うことができる」私自身も2人の子供の母親であるため、その見出しに興味を持ち、手に取ったこの本。内容は、不慮の事故により脳死状態となった幼い娘をこのまま生かすのか、臓器提供をするのか思い悩む母親の苦悩を描いたものである。
読み進めていくと、切なく苦しい思いになった。もし我が子だったらと思わずにいられないのだ。脳死となれば、子供の未来は無いに等しい。もう魂は身体に宿っていなくて、たくさんの生命維持装置に生かされ、眠りながら死を待つのだ。
客観的に考えれば、臓器提供をすれば、この世のどこかで、子供の心臓が生きていると考えられる。しかし、我が子となれば話は別だ。例え魂がなくとも、髪は伸びるし便をするのだ。身体の何処かしらが機能しているのに《脳死》と。
死という字を使うことがひどく非情に思える。我が子の命を親である自分が止めてしまう、そんな辛い選択をしないといけないのか。堂々めぐりの考えは、読み終わったあとでも答えは出なかった。
結局この母親は、娘自身が命を終わらせるまで側にいる覚悟を決め世話をするのだが、そうする事で家族内に溝が出来てしまう。眠ったままの娘を車椅子で連れて歩く事で、息子がいじめに合ってしまうのだ。夫に娘はもう死んでいるのだ。
生かすのは親のエゴではないか?と言われ、母親は狂っていく。とうとう警察を呼び、脳死である娘を今ここで刺した場合、殺人罪になるのか、ならないのかで、娘が今生きているのか死んでいるのかを証明しようとしたのだ。
脳死という判定が曖昧である日本では、こういうことが実際起こりうるのではないだろうか?的確な基準が必要なのではないだろうか?と思わず考え込んでしまった。
しかし、今回この作品は脳死してしまった母親側から書かれているため、母親に共感出来るが、もし我が子がドナーを待っている側だったらどうだろう。先ほどまで感じていた共感は消え、この子が提供してくれれば我が子は助かるかもしれないのに、と簡単に間逆の考えになるのだ。
それほど親と言うものは子供のためなら、いかに単純で、いざというときは手段を選ばずにいられるのだろう。それが周りから見れば、どんなに狂っていようが、それが親なのだと痛感した。子供は、時には言うこときかないし、イライラさせられることも多いと思う。
しかし、イライラするのも愛情があるからで、無関心ではいられないからなのだ。いつ、事故や病気で子供の笑顔が奪われるのか分からない。この本を読んで、子供たちとの時間をもっと大切に過ごしていこうと思った。
(20代女性)
「人魚の眠る家」の読書感想文③
この本を読み解くポイントは、登場人物の誰の立場や感情が一番近くに感じ、考えられるかではないか。また自らの価値観を一旦外に置き、様々な立場で想像をすることにより、興味深く読み進めることが出来るはずだ。
一つ一つの文章から、詳細な行動が頭の中に描かれる。複雑な気持ちも入ってくる。そして考えながらページを捲る。読むにつれ、嫌悪を抱くこともある。おそらく自らの無知と、価値観を拭いきれていないからだろう。
人間の未知なる部分が多く、人間の温かさと冷たさなど、二面性の対比が上手く描かれている。解明されていない生命の神秘と、科学的な根拠、その両方ともを信じたくなるような作品だ。絶望も希望も含まれている。
『生きる』とは『死ぬ』とはどういうことか、偉大なテーマに、様々な考え方を否定することなく向き合っている。日常のほんの些細な、誰にでも起こり得る事故から、ある家族の人生が変わった。
子どもへの愛か自己満足か、悩みながらも生きてゆく母。狂気にも満ちていく姿、葛藤。翻弄される家族や周囲の人々。しかしそれぞれにも強い思いや意志が感じられる。作品の中で人が生きている。
何が正しいかわからない、正解もない、人は自分が思うように、自分を信じるしかないのだ。最初から最後まで、色んな事に悩む登場人物たち。一つの悩みがさればまた別の悩みを持つ。悩みはつきず、それでも生きる。
悩みがあるというのは生きているからだろうか。では、悩む事すら出来ない状態は、生きていると言えるのだろうか。『生きる』ことについて考え抜く、難しく重いテーマである。人間とは不完全であり、不完全な人間の世界、そこにはもう一つの現実の世界が、繰り広げられていた。
作品を読み終えた時、世の中の人々への問いかけを感じるとともに、登場人物のそれぞれの感情を想像し、涙した。とても一言では言い表せないほどの、何とも言えない感情が胸をいっぱいにした。
人間は自分勝手な生き物だ。自らを含めてそう思う。現代人は人への関心が強く、人の心への関心が少ないように感じる。もっと相手の立場で物事を考えたり想像したり、価値観を広げなけばならない。単純に面白いというものではなく、常に考えされられる、そんな作品である。
(30代女性)
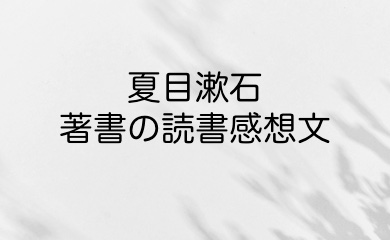
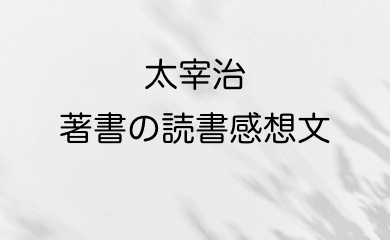
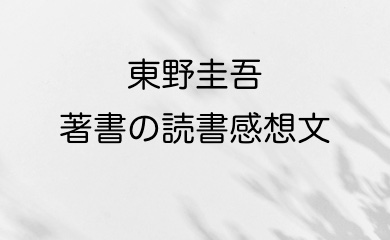
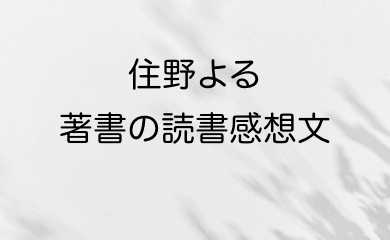





















Audibleで本を聴こう
Amazonのオーディオブック「Audible」なら、移動中や作業中など、いつでもどこでも読書ができます。プロのナレーターが朗読してくれるのでとっても聴ききやすく、記憶にもバッチリ残ります。月会費1,500円で、なんと12万以上の対象作品が聴き放題。まずは30日間の無料体験をしてみよう!!